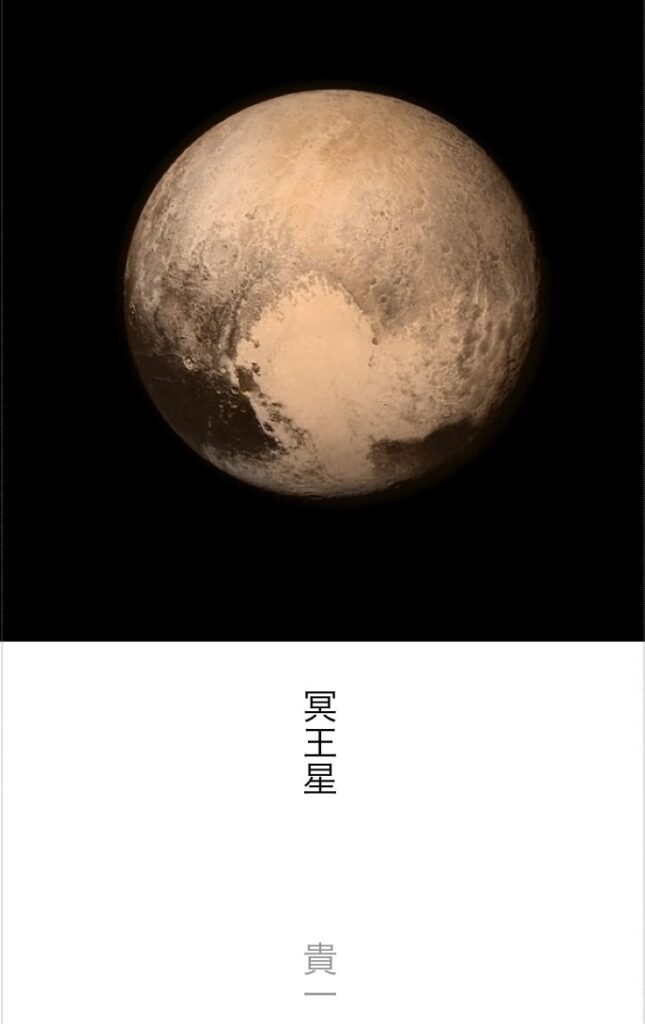――記憶と責任の海底で、人はなぜ生き延びてしまうのか
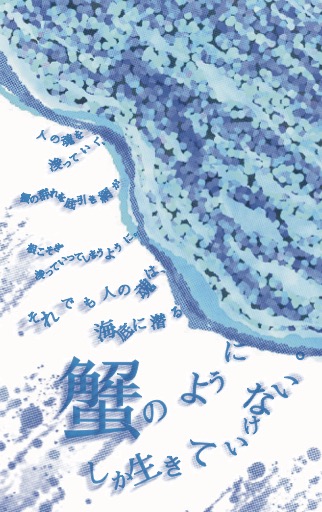
<私家本>
本作の長大なタイトルは、比喩である以前に、すでに倫理的宣言である。「人の魂を浚っていく」という暴力的な運動と、「それでも蟹のようにしか生きられない」という諦念。その二つが一息に結ばれたこの一文は、救済や成長、和解といった物語的快楽を、最初から読者に許さない。
物語の中心にいる津田は、破綻した人生を生きる人物ではない。広告代理店に勤め、家庭を持ち、夜には皇居を走る。彼は社会的には「問題のない側」に属している。しかし本作が描くのは、問題を起こした者ではなく、問題を見ないことで秩序を維持してきた者の不安である。
同窓会という平凡な場で語り出される小学校時代の記憶――教師による逸脱、少女の転校、沈黙を強いられた空気――は、三十年の時間を経てなお回収されない。ここで重要なのは、暴力が再発見されることではない。それが、長いあいだ「なかったこと」として社会の底に沈められてきた事実である。
津田は正義の告発者ではない。彼は、行方不明になった同級生・神尾(山根)を「気にしてしまう」だけの男だ。連絡を取り、住所を辿り、管理人に話を聞く。その行為は誠実に見えるが、同時にどこか居心地が悪い。なぜなら津田自身も、かつて起きていたことを「知らなかった側」「見なかった側」に属しているからだ。
本作における社会の比喩は明確である。それは底引き網だ。底引き網は、善悪も、罪も、無垢も選別しない。海底の生を一括して掬い取り、破壊する。学校制度、再開発される街、更新されていく秩序――それらはすべて、誰の魂が失われたのかを記録しない装置として機能している。
そのなかで生き残った者たちは、蟹のように海底に潜む。蟹は前に進まず、横に這い、殻を背負い、捕食される存在だ。津田もまた、主体的に未来へ向かう英雄ではない。彼は記憶の海底を横歩きし、ときおり真実の光に照らされては、また暗がりへ戻っていく。
この小説が特異なのは、ここからケア(世話・心配・配慮)という行為そのものを問いに晒す点にある。津田と妙子の行動は、現代的な言葉で言えば「アダルトナーシング」である。自立しているはずの他者を気にかけ、支えようとする行為。しかし本作は、それを倫理的に称揚しない。
ラカンの理論を参照すれば、ケアはしばしば「他者の欲望を欲望する」構造を持つ。津田は神尾を救おうとしているのではない。彼は、神尾という不在をめぐって動いている自分自身の位置にとらわれている。行方不明の神尾は、欲望を駆動する〈対象a〉として機能し、決して回収されない。
アダルトナーシングの最大の危険性は、それが善意の顔をしている点にある。世話する主体は、相手の欠如を埋めるふりをしながら、無意識のうちに快を得る。ラカン的に言えば、それは享楽(ジュイサンス)であり、そこに入り込んだ瞬間、ケアは暴力へと転じる。
本作で神尾は、次第に実体を失っていく。虚偽の住所、存在しない居住記録、回収されない痕跡。彼女は「語られる存在」ではなく、「語るための空白」となる。ここにおいてケアは、相手を沈黙させる力として働く。津田は介入しすぎないが、それでも神尾を「意味づけの対象」にしてしまう。
だからこそ、この物語には救出も解決もない。誰も完全には救われない。それは失敗ではなく、本作の倫理である。「それでも人の魂は、蟹のようにしか生きていけない」という一文は、他者を完全に救えないこと、欠如を埋められないことを引き受けた主体の姿を示している。
『冥王星』が〈周縁に追放された存在〉を描いた作品だとすれば、本作は〈周縁にいながら加担してしまう者〉の物語である。善でも悪でもない、多数派の位置。その曖昧で不快な場所を、貴一は逃げずに描いた。
この小説は、読者に理解や慰めを与えない。代わりに、理解していなかったこと、黙って通り過ぎてきたことの量を突きつける。その不快さこそが、本作の文学的誠実さである。
蟹は救われない。
だが、蟹であることを否定しない文学が、ここにある。